シニア犬の飼い主にとって、愛犬の食事管理は大きな課題です。年齢とともに変化する健康状態に合わせて、適切な栄養の摂取が欠かせません。この記事では、シニア犬のための手作りドッグフードの基本を紹介します。本記事を読めば、愛犬の健康状態に合わせた栄養バランスの良い手作りドッグフードの基礎が学べます。
手作りドッグフードは、愛犬の健康状態に合わせて調整できるのが大きなメリットです。必要な栄養素を理解したうえで、適した食材を選びましょう。
ドッグフードを手作りするメリット

ドッグフードの手作りには、愛犬の健康と幸せを考える飼い主にとって以下のメリットがあります。
- 食材を自由に選べる
- 愛犬の健康状態に合わせて調整できる
- 水分補給がしやすい
- 添加物を避けられる
食材を自由に選べる
手作りドッグフードは、食材を自由に選べることが最大のメリットです。愛犬の好みや健康状態に合わせて、最適な食材を選べます。食材を自由に選べるので、アレルギー対応も可能です。特定の食材を避けたり、必要な栄養素を意識して選ぶことができます。季節の新鮮な食材や高品質なタンパク質を含む食材、有機・無農薬の食材も使えます。
食材の原産地や品質を確認できるため、安全性の高い食事を提供できます。愛犬の体調に合わせて食材を調整でき、栄養バランスを整えられます。愛犬の好みに合わせて味や食感を工夫すると、食事の満足度も高まります。
愛犬の健康状態に合わせて調整できる
手作りドッグフードは、愛犬に合わせて内容を調整できる点が大きなメリットです。年齢や体重、健康状態に応じて食事内容を変更でき、愛犬に最適な栄養を提供できます。アレルギーがある場合は、該当する食材を除外しましょう。シニア犬になると食べ物の好き嫌いが激しくなったり、食べムラがでることもあります。その場合もメニューや量の変更で対応できます。味や食感を工夫することで、食事の楽しみを維持しやすくなります。
消化器系に合わせた調理法の変更やサプリメントの追加も、健康維持に効果的です。高齢犬の場合は、消化しやすい食材を選び、軟らかく調理すると食べやすくなります。若い犬や活動量の多い犬には、より多くのカロリーと栄養を含む食事を与えましょう。腎臓や肝臓に問題がある場合、負担をかけない食材の選択が大切です。
水分補給がしやすい
シニア犬になると保水力が落ちたり、自ら水を飲む量が減ったり、身体の不自由さなどから水が飲みにくくなる場合があります。手作り食なら食事から水分を摂取できるため、脱水予防に役立ちます。
犬が1日に必要な水分摂取量の目安は?
犬の1日の適切な飲水量は、体重1kgあたり約50~70mlが目安です。
体重5kgなら1日に250~350mlが目安になります。
ムチンを含む食材を摂取することで水分保持に役立ちます。ムチンは粘膜や唾液、涙などに含まれる糖タンパク質です。めかぶ、もずく、レンコン、納豆、山芋などネバネバした食材に多く含まれています。ムチンは熱に弱いため、加熱しすぎない調理法(汁ごと食べるレシピなど)が推奨されます。
水をあまり飲んでくれない場合は、水に味をつける方法もあります。油の少ない肉のゆで汁や、カツオ節を少量混ぜるなど工夫してみましょう。
添加物を避けられる
手作りドッグフードであれば、不要な添加物を避けられます。市販品では、以下のような添加物が含まれているドッグフードもあります。
- 人工保存料
- 人工着色料
- 化学調味料
- 人工香料
添加物には健康維持を目的としたものもあります。全ての添加物が健康に良くないわけではありませんが、長期的な健康維持を考えるとできるだけ避けたい成分もあります。
シニア犬は添加物に敏感な場合があるため、手作りドッグフードも選択肢のひとつです。
ドッグフードを手作りすると、危険性のある添加物を排除でき、愛犬の健康リスクを軽減できます。
添加物による味覚への影響も避けられ、愛犬が本来持っている食欲を引き出しやすくなります。安心できる食材を使い、安全なご飯を提供できるのは、大きな利点といえるでしょう。
ドッグフードを手作りするデメリット
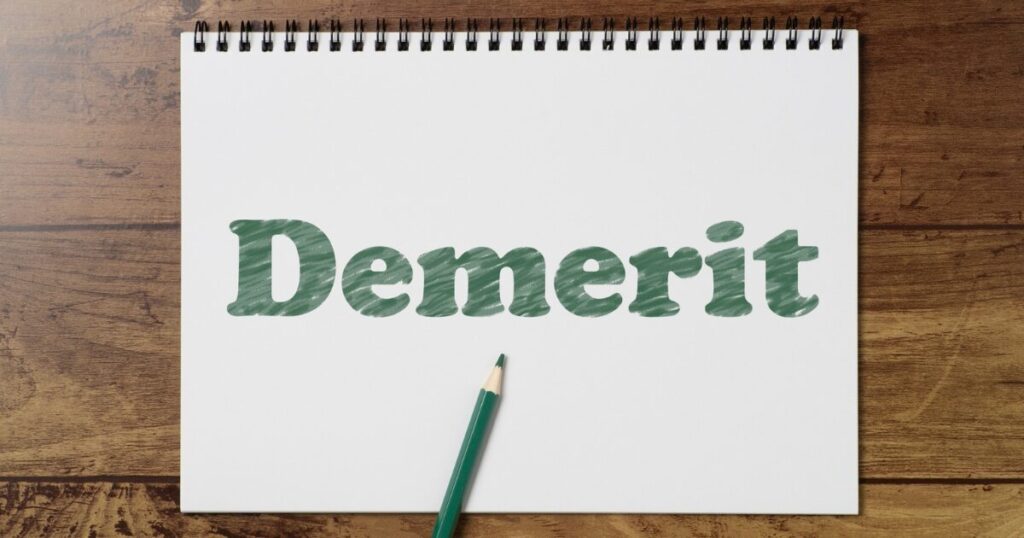
- 栄養バランスの管理が難しい
- 保存性が低く、手間がかかる
- 手間と時間がかかる
- 持ち運びが難しい
栄養バランスの管理が難しい
手作りフードではタンパク質、炭水化物、脂肪などの栄養バランスを整える必要があります。専門的な知識が必要で、市販フードほど簡単にはバランスが取れません。栄養不足や過剰摂取のリスクがあり、健康に影響が出る可能性もあります。犬に有害な食材があるため、与えてはいけない食材を選別する知識も必要です。
手作りフードは嗜好性が高いですが、栄養バランスを保つのが難しいため、市販のフードと組み合わせることでバランスを取りやすくなります。総合栄養食は栄養バランスが計算されており、手作りフードで不足しがちな栄養素を補うことができます。
保存性が低く手間がかかる
手作りドッグフードは市販品と比べて保存期間が短く、作り置きをする場合も冷蔵・冷凍保存が必要です。冷凍保存した場合も、長期間保存すると風味や栄養価が落ちるため、早めに使い切ることが推奨されます。冷凍庫の保存スペースが必要になるのもデメリットのひとつです。
停電や災害時に備えて、保存方法を考えておく必要があります。市販のフードならストックしやすいですが、手作り食の場合は非常食の準備が難しくなるため、緊急時の対応を考えておくことも重要です。
手間と時間がかかる
毎回の食事を手作りする場合、調理や後片付けの手間がかかります。栄養バランスを考えながら作る必要があるため、レシピを考えたり、食材を準備したりする時間も必要です。特に忙しい日や体調がすぐれないときには、手作りご飯を続けるのが負担になることもあります。
継続には、市販フードとの併用や冷凍保存の活用など、無理のない工夫が必要です。
持ち運びが難しい
旅行やペットホテルに預ける際、手作りご飯を持参するのは手間がかかります。市販のドライフードと比べるとかさばりやすく、保存方法にも気をつけなければなりません。ペットホテルでは、手作りご飯の持ち込みができない場合もあるため、事前に確認しておく必要があります。
手作りドッグフードは、愛犬の健康を考えた食事を提供できる魅力的な選択肢ですが、栄養バランスの管理や手間などのデメリットもあります。飼い主側の知識と準備も重要です。獣医師や専門家に相談しながら、適切な情報収集を行い、愛犬に合った方法を取り入れることが大切です。
ドッグフードを手作りする前にやるべきこと

シニア犬のための手作りドッグフードを始める前には、獣医師や動物栄養士に相談し、愛犬の状態を確認しましょう。犬に必要な栄養を理解するだけでなく、必要な道具の準備も、手作りドッグフードを始めるうえで大切です。適切に準備を整えれば、安全に手作りドッグフードを始められます。
犬に必要な栄養を理解する
手作りドッグフードを始める際は、犬に必要な栄養素の理解が重要です。愛犬の健康を維持するには、バランスの取れた栄養摂取が欠かせません。犬に必要な主な栄養素は以下のとおりです。
- タンパク質
- 炭水化物
- 脂肪
- ビタミン
- ミネラル
- 食物繊維
- 水分
タンパク質は犬の体を構成する重要な要素なため、十分な量を与えましょう。年齢や健康状態に応じた栄養バランスの調整も大切です。シニア犬の場合、消化機能が低下している場合が多いため、消化しやすい食材を選びましょう。
栄養バランスの調整が難しい場合は市販フードと併用して栄養バランスを調整しましょう。
必要な道具をそろえる
シニア犬のための手作りドッグフードを始める前には、必要な道具をそろえてください。適切な道具があれば、調理がスムーズに進み、衛生的に食事を準備できます。必要な道具は、以下のとおりです。
- 計量器具
- 保存容器
- 耐熱ボウル
計量器具は、正確な栄養バランスを保つために必要です。ゴム手袋やペーパータオルなどの衛生用品も、忘れずに準備しましょう。
歯の弱ったシニア犬や飲み込みが苦手な子には、食材を細かくしたりペースト状にしたりする工夫が必要です。ブレンダーを使えば、食べやすさの調整がしやすくなります。飼い主用の食事を下準備する際に、味付け前に犬用として取り分けてブレンダーで調整することもできます。包丁で細かく刻む、フォークで潰すなどの方法もありますが、均一なペースト化は困難です。以下の場合はブレンダーがあると便利です。
ブレンダーがあると便利なケース
- 消化機能の低下
老犬は噛む力や消化能力が衰えるため、食材をペースト状にすることで消化負担を軽減できます。飲み込む力が衰えて食べづらくなると食材を細かくすりつぶす必要があります。シリンジや容器を使って介助が必要な場合も役立ちます。 - 食事の濃度調整が柔軟にできる
体調不良時や脱水気味の際、水分量を調整したポタージュ状の食事を提供できます。状態に応じて濃度が調整できます。 - 飼い主用の食事と一緒に準備したり、多頭飼いにも対応できる
健康な犬と老犬が同居する場合、同じ食材をブレンダー処理で形状変更し、個別対応が可能になります。
食材の鮮度を保つための保冷バッグや、調理後の保存に便利なラップフィルムやアルミホイルも用意すると便利です。調理用温度計があれば、食材の加熱状態を確認でき、安全性が高まります。
手作りドッグフードにおすすめの食材と避けるべき食材

手作りドッグフードは、愛犬の栄養バランスを考慮して食材を選べるメリットがあります。おすすめの食材だけでなく、避けるべき食材もあるため、注意してください。
おすすめの食材
高齢の愛犬の健康維持に役立つ食材は、以下のとおりです。
- 鶏むね肉、ささみ、牛赤身
- 白身魚、サーモン
- ブロッコリー、ホウレンソウ
- 玄米、オートミール
- リンゴ、ブルーベリー(種・芯は避ける)
- 無糖ヨーグルト、カッテージチーズ(乳糖耐性を確認する)
- オリーブオイル、ココナッツオイル(ごく少量)
タンパク質源としては、皮なしの鶏肉や脂肪分の少ない部位の牛肉がおすすめです。魚類では、良質なタンパク質と健康的な脂肪を含むタラやヒラメ、白身魚、サーモンが適しています。ブロッコリーやホウレンソウ、カボチャ、ニンジンは、食物繊維とビタミン、ミネラルが豊富です。
炭水化物源としては、玄米やオートミール、サツマイモが消化しやすく、エネルギー源として優れています。リンゴやブルーベリーなどの果物は、抗酸化物質が豊富で、シニア犬の健康維持に役立ちます。乳製品では、良質なタンパク質とカルシウムを含む無糖ヨーグルトやカッテージチーズを選びましょう。
健康的な脂肪源としては、オリーブオイルやココナッツオイルがおすすめです。
※アレルギーや持病がある場合は、必ず獣医師に相談しましょう。
避けるべき食材
シニア犬の健康を守るために、避けるべき食材は以下のとおりです。
- チョコレート
- タマネギ
- ニンニク
- ブドウ
- レーズン
- マカダミアナッツ
- アボカド
- キシリトール入り食品
消化器系や神経系に悪影響を及ぼす食材も多くあるため、注意しましょう。生肉や生魚、生卵、高脂肪の食品、塩分の多い食品、カフェイン含有食品、アルコールも避けるべきです。シニア犬の消化器系に負担をかけたり、体調を崩す原因になります。
骨付き肉やパン生地、トマトの茎や葉なども避けるべき食材です。誤って食べてしまうと、窒息や消化器系のトラブルを引き起こす恐れがあります。シニア犬の健康を守るために、与える食材には十分に注意しましょう。
手作りドッグフードのレシピ

シニア犬のための手作りドッグフードでは、年齢や健康状態に合わせて栄養バランスの取れた食材を選んでください。調理するときは食材を小さく切って柔らかく煮込み、食べやすい形状にしましょう。
タンパク質メインのレシピ
シニア犬にとって、筋肉量の維持はとても大切です。タンパク質を効率的に摂取できるレシピは、シニア犬の健康維持に役立ちます。
- 鶏肉とブロッコリーのやわらか煮
- サーモンとサツマイモのオーブン焼き
- 牛ひき肉と野菜のミートローフ
鶏肉とブロッコリーのやわらか煮
ササミや鶏胸肉など脂肪が少なく、消化しやすい部位がおすすめです。ブロッコリーには食物繊維やビタミンCが含まれ、腸内環境をととのえるサポートをしてくれます。小さくカットして、しっかり煮込むことでシニア犬にも食べやすくなります。
サーモンとサツマイモのオーブン焼き
サーモンに豊富なオメガ3脂肪酸(DHA・EPA)は、関節や皮膚の健康をサポートしてくれます。サツマイモはエネルギー源になりつつ、やさしく腸に届く炭水化物。皮をむいて薄くスライスし、蒸してから軽く焼くと香ばしくなります。
牛ひき肉と野菜のミートローフ
牛肉は鉄分やビタミンB群も豊富。にんじんやズッキーニなどの野菜と一緒に混ぜてオーブンで焼けば、香りもよく、栄養バランスのとれた一品になります。しっかり加熱して、食べやすくスライスしましょう。
鶏肉やサーモン、牛肉は良質なタンパク質源です。野菜と組み合わせると、さまざまなビタミンやミネラルを摂取できるバランスの良いメニューになります。
野菜と果物を使ったレシピ
シニア犬の健康維持には、野菜や果物を取り入れたレシピがおすすめです。野菜や果物にはビタミンやミネラル、食物繊維が豊富に含まれており、愛犬の体調管理に役立ちます。おすすめのレシピは、以下のとおりです。
- 野菜スープ
- グリーンスムージー
- ベジタブルチップス
- フルーツヨーグルト・フルーツアイス
野菜スープ
キャベツ・にんじん・かぼちゃなどを細かく切って煮込んだやさしいスープ。シニア犬の水分補給にもぴったりです。塩分やだしは使わず、素材の甘みを活かしましょう。
グリーンスムージー
小松菜やリンゴ、バナナを少量の水でペースト状にしたスムージーは、トッピングやおやつ代わりにおすすめです。糖分が多くならないように、量には気をつけましょう。
かぼちゃ・にんじんチップス
かぼちゃやサツマイモ、薄切りにしたにんじんをオーブンで焼いたチップスは、無添加の安心おやつになります。固さは歯の状態に合わせて調整してください。
フルーツヨーグルト・フルーツアイス
無糖のヨーグルトに、りんごやブルーベリーを少し加えたフルーツヨーグルトは、乳酸菌もとれる一品です。夏にはフルーツをペースト状にして冷凍したアイスも喜ばれます。ただし、果物は糖分があるため、与えすぎには注意しましょう。
愛犬の好みや健康状態に合わせて、食材や調理方法を調整してください。野菜や果物を使ったおやつも、シニア犬の健康維持に役立ちます。
フルーツアイスやフルーツヨーグルトなどが人気ですが、糖分の摂りすぎには注意が必要です。野菜のムースやパテも、シニア犬の食事バリエーションを増やすために役立ちます。柔らかくて食べやすい食事は、歯の弱くなったシニア犬に適しています。
米やサツマイモを使ったレシピ
シニア犬のための栄養バランスの取れた食事として、米やサツマイモを使ったレシピがおすすめです。米やサツマイモは消化しやすく、エネルギー源として適しています。米やサツマイモのレシピは、以下のとおりです。
- 鶏肉と米のおかゆ
- サツマイモと鶏ひき肉のグラタン
- 白身魚と米のリゾット
- サツマイモとツナのキャセロール
鶏肉と米のおかゆ
鶏肉をゆでて細かく裂き、炊いたお米と一緒に煮込んだおかゆは、食欲が落ちがちな子にもぴったり。水分も多く、消化を助けてくれます。
サツマイモと鶏ひき肉のグラタン風
マッシュしたサツマイモに鶏ひき肉を加えてオーブンで焼くだけの簡単レシピ。サツマイモにはビタミンAが多く含まれ、目や皮膚の健康維持に役立ちます。
白身魚と米のリゾット
タラやスズキなどの白身魚は、脂肪分が少なく消化にやさしい食材です。炊いた米と一緒に煮て、リゾット風にすれば、香りも良く食いつきもアップします。
サツマイモとツナのキャセロール
無塩のツナとサツマイモを混ぜて焼いたレシピは、おやつにも軽食にも◎。塩分・油分の少ないツナを使いましょう。
レシピを選ぶときは、愛犬の好みや健康状態に合わせて調整してください。獣医師に相談しながら、最適な食事プランを立てましょう。
手作りドッグフードの保存方法と衛生管理

手作りドッグフードの保存方法と衛生管理は、愛犬の健康を守るために重要です。適切な保存と衛生管理により、安全でおいしい手作りドッグフードを与えましょう。
保存方法と保存期間
手作りドッグフードは保存料を使っていない分、どうしても傷みやすくなります。まずは基本的な保存方法と消費期限をしっかり押さえておきましょう。
- 冷蔵保存:当日〜翌日に使い切りましょう。
- 冷凍保存:1週間程度が目安です。解凍後の再冷凍は避けてください。
密閉容器やジップロックを使って小分けにし、日付ラベルを貼って管理すると便利です。製氷皿での冷凍も、与える量の目安にもなって便利です。室温での長時間の放置は避けてください。冷めにくい場合は氷や保冷剤を入れたボウルなどにいれて冷やしましょう。
手作りご飯の保存期限が短い理由
「どうしてこんなに早く使い切らないといけないの?」と思われるかもしれませんが、犬の手作りご飯の保存期限が短い理由には、いくつかの要因があります。
- 塩分が控えめ:犬用ごはんは塩分をほとんど使わないため、保存性が低くなります。
- 水分が多い:調理済みの食事は水分を多く含むため、細菌が繁殖しやすくなります。
- 複数の食材を使用:肉や魚、野菜など保存特性の異なる食材が混ざっており、傷みやすいものに合わせて管理する必要があります。
- 栄養価と風味の変化:冷凍期間が長くなると、栄養価や香りが落ちてしまい、愛犬の食いつきにも影響が出ることがあります。
- 衛生面からの配慮:何より大切なのは、食中毒などのリスクを防ぎ、安心して与えられる状態を保つことです。
冷凍保存でも1週間以内に使い切ることが推奨されています。この期間内に使い切ることで、栄養価や風味を最大限に保ち、愛犬に安全で美味しい食事を提供することができます。
保存期限内であっても臭いや変色が気になる場合は、安全のために廃棄してください。愛犬の健康を第一に考えて、適切な保存管理を心がけましょう。
衛生管理のポイント
シニア犬の健康を守るためには、衛生管理が重要です。適切な衛生管理により、食中毒や感染症のリスクを減らせます。以下のポイントに注意しましょう。
- 調理器具や調理スペースを清潔に保つ
- 新鮮な食材の選択と洗浄
- 調理前・調理中のこまめな手洗い
- 肉類の十分な加熱
- 調理後はすぐに冷ます
冷蔵庫内での適切な保存が大切です。清潔で、密閉できる保存容器を使用してください。古くなったものは廃棄しましょう。調理器具や保存容器、食器の定期的な消毒も必要です。調理や取り分けの際は、清潔な箸を使用してください。生の状態の食材に触れた箸は、加熱後の食材には使わず、別の清潔な箸に取り替えましょう。衛生管理をしっかり行えば、安心してシニア犬に手作りドッグフードを与えることができます。
手作りドッグフードを続けるコツ

手作りドッグフードを無理なく続けるためのコツを紹介します。ドッグフード作りをルーティン化し、愛犬の反応を励みにしながら続けましょう。
調理の手間を減らす
調理の手間を減らすのは、手作りドッグフードを続けるうえで重要なポイントです。効率的な方法を取り入れると、手作りドッグフードを続けやすくなります。調理の手間を減らすポイントは、以下のとおりです。
- まとめて作って冷凍保存
- 簡単なレシピ選び
- 調理器具や調理家電の活用
- 下ごしらえを効率的に行う
- カット済み野菜など、便利な食材の利用
複数の方法を組み合わせると、日々の調理時間を大幅に短縮できます。電気圧力鍋を使って大量調理するなど、週末に食材をまとめて下ごしらえすれば、平日の負担を減らせます。同じ食材でアレンジできるレシピをローテーションすると、買い物や調理の効率化が可能です。
食洗機で洗える調理器具を選べば、後片付けの手間を減らせます。シニア犬の手作りドッグフードを無理なく続けるために、調理の手間を減らす工夫を取り入れてましょう。
手作りドッグフードに関するよくある質問

手作りドッグフードに関する疑問や不安を解消するために、よくある質問と回答をまとめました。シニア犬の健康を守るための参考になればうれしいです。
手作りドッグフードは毎日与えてもいい?
手作りドッグフードは毎日与えられますが、栄養バランスに注意が必要です。手作りドッグフードを毎日与えるときは、獣医師や動物栄養士に相談し、犬の年齢や健康状態に合わせて調整してください。忘れずに、定期的に健康チェックをしましょう。
適切な栄養バランスの維持が難しい場合もあるため、市販のドッグフードとの併用もおすすめです。急激な切り替えは避け、徐々に移行しましょう。手作りドッグフードの量や頻度は、犬の体重や活動量に応じて調整する必要があります。
シニア犬の場合、消化機能の変化に合わせた食材選びやカロリー調整などに注意が必要です。愛犬の健康を第一に考え、専門家のアドバイスを受けながら進めましょう。
手作りドッグフードへの切り替え方は?
手作りドッグフードに切り替える際は、愛犬の健康を考えて慎重に行ってください。急激な変更は消化器系に負担をかける可能性があるため、1〜2週間かけてゆっくり進めましょう。最初は市販フードに手作りフードを少量トッピングし、体調に問題がないか確認します。問題がなければ、手作り25%、従来のフード75%の割合から始め、数日ごとに手作りの割合を少しずつ増やします。
切り替えのときは、愛犬の体調変化を観察しながら進めましょう。活動量や毛並み、便の質、体重の変化に注意してください。下痢や嘔吐などの症状が見られた場合は、切り替えのペースを遅くしてください。完全に切り替わるまでには時間がかかる場合もあるため、根気強く続けましょう。不安点があれば、獣医師に相談してください。
手作りドッグフードと市販のドッグフードは併用できる?
手作りドッグフードと市販のドッグフードの併用は問題ありません。むしろ、栄養バランスや調理の負担を考慮すると、併用には多くのメリットがあります。市販のドッグフードと併用するメリットは、以下があります。
- 栄養バランスの調整がしやすい
- 消化器系への負担軽減
- 手作りフードで不足しがちな栄養素の補完
- 時間や労力の節約
- 愛犬の好みや健康状態への柔軟な対応
手作りフードと市販フードを併用する際の具体的な方法は以下の通りです
- トッピング形式
- 市販フードに手作り食を少量トッピングします。例えば、茹でた鶏肉や野菜を細かく切り、フードに混ぜる形が簡単でおすすめです。
- 一部置き換え
- 朝は市販フード、夜は手作りごはんというように、1日の食事を分けて提供する方法もあります。
手作り食だけでは不足しがちな栄養素(ミネラルやビタミン)を補うため、市販フードは「総合栄養食」を併用することが重要です。 - 茹で汁の活用
- 手作りごはんの材料(鶏肉や野菜)を茹でた汁を市販フードにかけると、風味が増して食欲が向上します。食事から水分が摂取できるので水分補給にも役立ちます。
両方のカロリーを計算し、適切な量を与えてください。併用を始めるときは、少量の手作りフードを市販フードにトッピングする形で始め、少しずつ量を増やしましょう。併用の割合は、犬の年齢・体調・好みに合わせて調整してください。必要に応じて、獣医師のアドバイスを受けることをおすすめします。
定期的に愛犬の健康状態をチェックしてください。体重の変化や皮膚の状態、便の様子などを観察し、必要に応じて量やバランスを調整しましょう。
まとめ

手作りドッグフードのメリットは食材を自由に選べ、愛犬の健康状態に合わせて調整できることです。避けるべき食材に注意して、おすすめの食材を活用してください。
簡単なレシピから始め、徐々にレパートリーを増やしましょう。安全のため、適切な保存方法と衛生管理を心がけてください。無理なく続けるためには「完璧を目指さず、できる範囲で」が基本です。食事は段階的に切り替え、必要に応じて市販品と併用するなどの工夫をしましょう。
定期的に獣医師に相談し、愛犬の健康状態をチェックしましょう。愛犬の様子を見ながら、少しずつ楽しみながら続けてみてくださいね。


